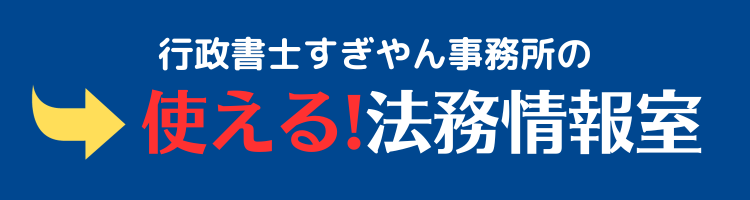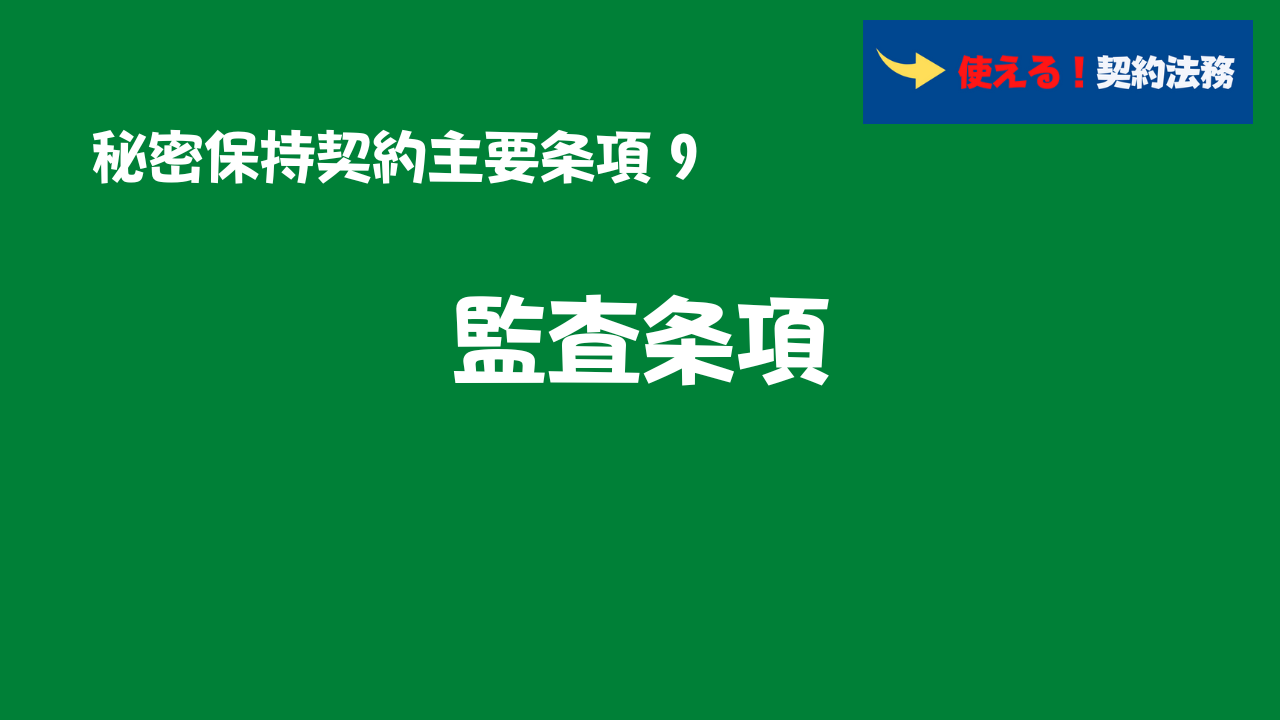秘密保持契約の主要条項解説シリーズ第9回は、監査に関する規定です。
監査に関する規定のサンプル
開示当事者は、事前に受領当事者に通知したうえで、秘密情報の管理状況を受領当事者の営業時間中に監査することができる。
監査に関する規定の内容
開示した秘密情報が相手方で適切に管理されているか、秘密情報が漏れていないか、秘密情報を流用していないかを、確かめるために実際に相手方を監査できるという条項が秘密保持契約に入っている場合もあります。
監査に関する規定のチェックポイント
監査条項で議論になりうるポイントは以下のとおりです。
• 監査実施日時はどうするか
• 誰が監査するか
• 監査費用の負担はどうするか
監査日時はどうするか
突然、現場に契約相手が監査に来ても、通常業務の邪魔になるし、資料や会場の準備などが煩雑で迷惑だという考えもあるでしょう。したがって「事前に通知したうえ監査する」とする場合が多いです。なお、監査に踏み込む5分前でも事前といえば事前ですので、監査予定日の10日前までに通知するなどと通知の時期を決めることも多いです。
事前通知があまりにも事前すぎると、その間に実態が是正され、正しい監査ができない恐れもあるし、逆にあまりに短いと、業務調整や会場等の準備が整わないということもあるので、契約交渉時に十分協議して適度な日数を設定するといいでしょう。
また細かいですが、ここが「通知」ではなく「承諾」となっている場合もあります。これも不当に承諾を拒絶されると、監査が実施できないことにもなりかねず、注意が必要です。
誰が監査するか
誰が監査するかといえば、基本は開示者自身が監査することが多いですが、監査法人や情報管理システムの技術者などの専門家に委託して監査を実施する場合もあります。
監査費用の負担はどうするか
監査を委託する場合など、監査には費用が生じる場合があります。この監査費用は監査を行う者が負担することが基本ですが、監査で契約違反が判明したときには、監査を受ける当事者の方が監査費用を負担するという規定をおく場合もあります。
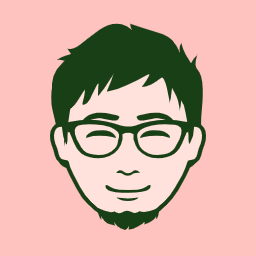
プロ野球のリクエスト制度のように、1年間に監査できるのは2回までとかいう制限をした方がいいかもしれませんね。

確かに、一つのアイデアですね。

行政書士すぎやん事務所に秘密保持契約の作成を依頼してみませんか。ホームページをご覧ください。